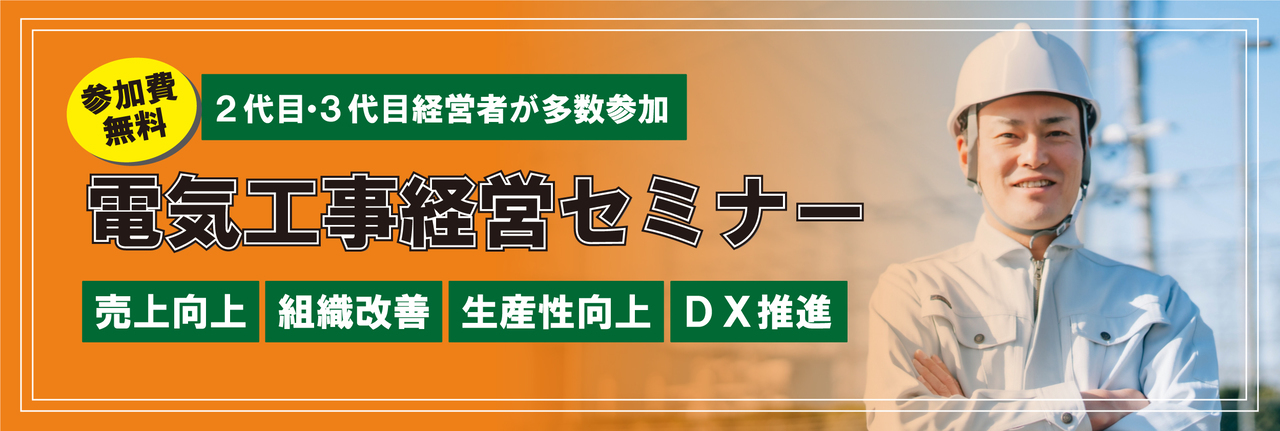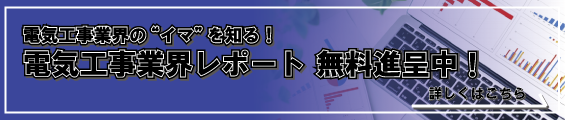電気工事会社の利益を増やす方法4選
電気工事会社専門のポータルサイト"電工広場"の経営コラムページに移転しました。
新しいページのURLはこちらです。
https://denkohiroba.com/detail_column/1698274631003x748802622937890800
新着情報・お知らせ
2023/10/09
11月1日(水)開催「電気工事・通信工事会社向け人材採用強化セミナー」のご案内を更新しました。
2023/09/09
電気工事・通信工事会社向けセミナー「材料コスト削減セミナー」のご案内を更新しました。
2023/09/05
電気工事・通信工事会社向けセミナーのご案内を更新しました。